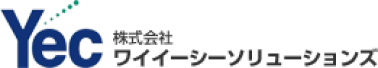自治体DXとは、どのようなものでしょうか。ここでは、自治体DXの概要と意義を解説します。
自治体DXの概要
自治体DXとは、デジタル技術を使って住民の利便性を高めたり、行政サービスの質を上げたりすることです。DXとは「デジタル・トランスフォーメーション(Digital Transformation )」を表しており、自治体のみならず民間企業も積極的に推進しています。
自治体DXの意義
総務省は2020年に、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を発表しました。「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指すとしています。
自治体DX推進の目的
自治体DXを推進する目的は複数あります。以下で詳しく解説します。
自治体職員数が減少しているため
自治体DXが注目されている背景には、自治体職員の減少が挙げられます。総務省が公表しているデータによると、2023年4月1日現在における地方公務員の人数は、280万1,596人でした。前年と比較すると2,068人も減少しています。職員数の減少により、職員1人あたりの業務負担が大きくなっている状況です。
※参考:地方公務員数の状況|総務省
少子高齢化対策のため
日本では少子高齢化が進み、労働人口が減少しています。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率が39%になるという推計を厚生労働省が発表しています。
特に、地方では少子高齢化が顕著です。また、都市部に人口が一極集中し、地方の財収は悪化しています。このような状況で自治体を維持存続するには、DXにより業務を効率化しなければなりません。
※参考:我が国の人口について|厚生労働省
自治体DX推進で重要な6つの取り組み項目
2020年12月、総務省は自治体DX推進計画を策定しました。この計画では、DXについて自治体が重点的に取り組むべき内容や、国の支援などがまとめられています。自治体の取り組みとして推奨されている6つの事項が記載されているため、以下で詳しく解説します。
自治体の情報システムの活用
基幹系20業務のシステムについて、2025年度中に、国が策定する標準仕様に準拠したシステムへの移行が求められています。現在は、同じ業務でも製品や自治体によってサービスに差が生じている状況です。システムの統一により、すべての自治体で同様のサービスが受けられるようになります。
※参考:地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁
マイナンバーカードの普及を促進
政府は、マイナンバーカードによる本人確認、認証機能をデジタル社会の基盤と捉えています。そのため、すべての国民に対してマイナンバーカードの所持を推奨しています。マイナンバーカードと健康保険証や運転免許証の一体化に取り組み、各種サービスの一本化や充実を目指している状況です。
行政手続きのオンライン化
マイナンバーカードの活用により、行政手続きのオンライン化も推進されています。マイナポータルを通じ、オンラインで各種手続きを行うための仕組みが模索されているところです。行政手続きのオンライン化により、窓口業務にかかる手間や時間の削減を期待できます。
自治体のAI利用促進
持続可能な行政サービスの提供を目指し、デジタル技術の積極的な活用が求められています。システムの標準化だけでなく、AIやRPAの利用促進による利便性の向上も期待されています。「RPA」とは「ロボティック・プロセスオートメーション(Robotic Process Automation)」を表しており、作業を自動化するソフトウェアロボットです。
AIやRPAは業務効率化に効果的で、すでに導入している自治体が多数あります。
テレワークの推奨
新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、民間企業ではテレワークが盛んになりました。自治体においても、テレワークの導入は少しずつ進んでいます。テレワークの導入により、働き方改革の推進や行政サービスの向上など、さまざまな効果が期待できます。
セキュリティ対策を徹底させる
自治体は個人情報を多く扱っているため、自治体DXの推進においては、セキュリティ対策の徹底も重要です。住民の個人情報が危険に晒されないよう、十分なセキュリティ対策に取り組まなければなりません。セキュリティポリシーの見直しや具体的な対策の強化が求められています。
自治体DXのステップ
自治体DXはどのように進めればよいのでしょうか。以下で具体的に解説します。
自治体DXを進める体制を整える
自治体全体でDXを推進するには、体制を整える必要があります。自治体の職員や関係者に対して自治体DXの説明や情報共有を行い、認識を高めましょう。また、自治体DXを進めるには、各部署で役割を決めることも大切です。
DXに詳しい人材を育成する
DXの推進には専門的な知識やスキルが必要なため、民間企業の力も借りながら人材の確保や育成に取り組むべきです。外部の専門家と連携し、技術やノウハウの取得を目指しましょう。
現行業務を整理する
自治体DXに取り組むうえでは、自動化できるノンコア業務を検討しましょう。業務の量や手順を可視化し、コア業務とノンコア業務を分類するところから始めます。そのうえで、現在の業務の過不足や無駄を見直していきます。
自治体DXのメリット
自治体DXに取り組むと、さまざまなメリットが期待できます。以下で詳しく解説します。
業務効率化につながる
自治体DXを推進すれば、業務効率化を実現できます。例えば、行政手続きをオンライン化した場合、窓口業務の減少により、それまでかけていた手間や時間を削減できます。また、情報のデータ化によって、自治体の内部における情報共有もスムーズになるでしょう。
地域経済の発展につながる
自治体DXに取り組むと、IoTによるスマートシティの構築や、AIの活用による防犯・防災対策などを実現可能です。それにより住民の生活の質が向上し、地域全体の魅力も高まると考えられます。その結果、優秀な人材の流入や民間企業の誘致の成功なども期待できます。自治体DXは、地域経済の発展にも貢献するでしょう。
自治体DXの課題
自治体DXに取り組むうえでは課題もあります。以下で詳しく解説します。
アナログ文化が根付いている
自治体の中にはアナログ文化が根付いており、現在でも紙によるやり取りがメインになっているケースが見られます。デジタルへ移行するには人材の確保が必要であることから、一時的に業務量も増加します。そのため、自治体DXの重要性は理解していても、躊躇する自治体は少なくありません。
デジタル化に対応できる人材が不足している
デジタル化に対応できる人材が不足している自治体も多いようです。デジタル化においては、住民がメリットを得られるデザインや設計が必要となります。人手不足の状況ではそのような対応が難しく、既存業務への対応で手一杯な自治体も珍しくありません。
自治体DXの取り組み事例
積極的に自治体DXを推進しているところも増えています。ここでは、自治体DXの事例を紹介します。
川越市斎場
川越市斎場ではもともと電話で予約を受け付けており、受付事務の負担が大きい状況でした。そこで、施設の予約受付とともに、施設の使用料の収納管理、利用申請・許可にも対応できる『Seagull-LC 斎場施設システム』を導入して活用しています。その結果、職員の事務作業にかかる手間や時間を大幅に削減できました。
相模原市
相模原市では、市民の意見を聞く手段として、手紙やFAXが利用されていました。比較のために過去に届いた意見を探す際は、手作業で対応しなければならない全体の傾向や進捗の把握も困難でした。
2014年4月から「市民の声システム」を導入したことで、担当者の業務効率が改善されています。データ化により文書の流用や閲覧も容易になりました。
藤沢市
藤沢市ではシステム業務の拡張に伴い、人手不足の問題が発生していました。そのため、業務運用サービスを導入したところ、主業務のIT戦略の企画立案・行政サービスに職員が専念できる環境を整えられています。
まとめ
職員数の減少や少子高齢化などの影響により、自治体の業務にもさまざまな影響が出てきています。その対策として、自治体DXが推進されています。自治体DXに取り組むと業務効率化になるだけでなく、住民の利便性や満足度も向上する可能性が高いです。
Seagull-LC 斎場予約システムは、斎場施設の業務を総合的にサポートできるツールです。全国シェアNo.1を誇ります。その他にも自治体DXに役立つさまざまなシステムがあるため、自治体DXを推進したいと考えているご担当者の人は、ぜひご相談ください。
\システムを詳しくご紹介しています/