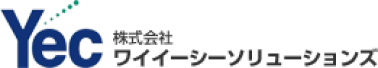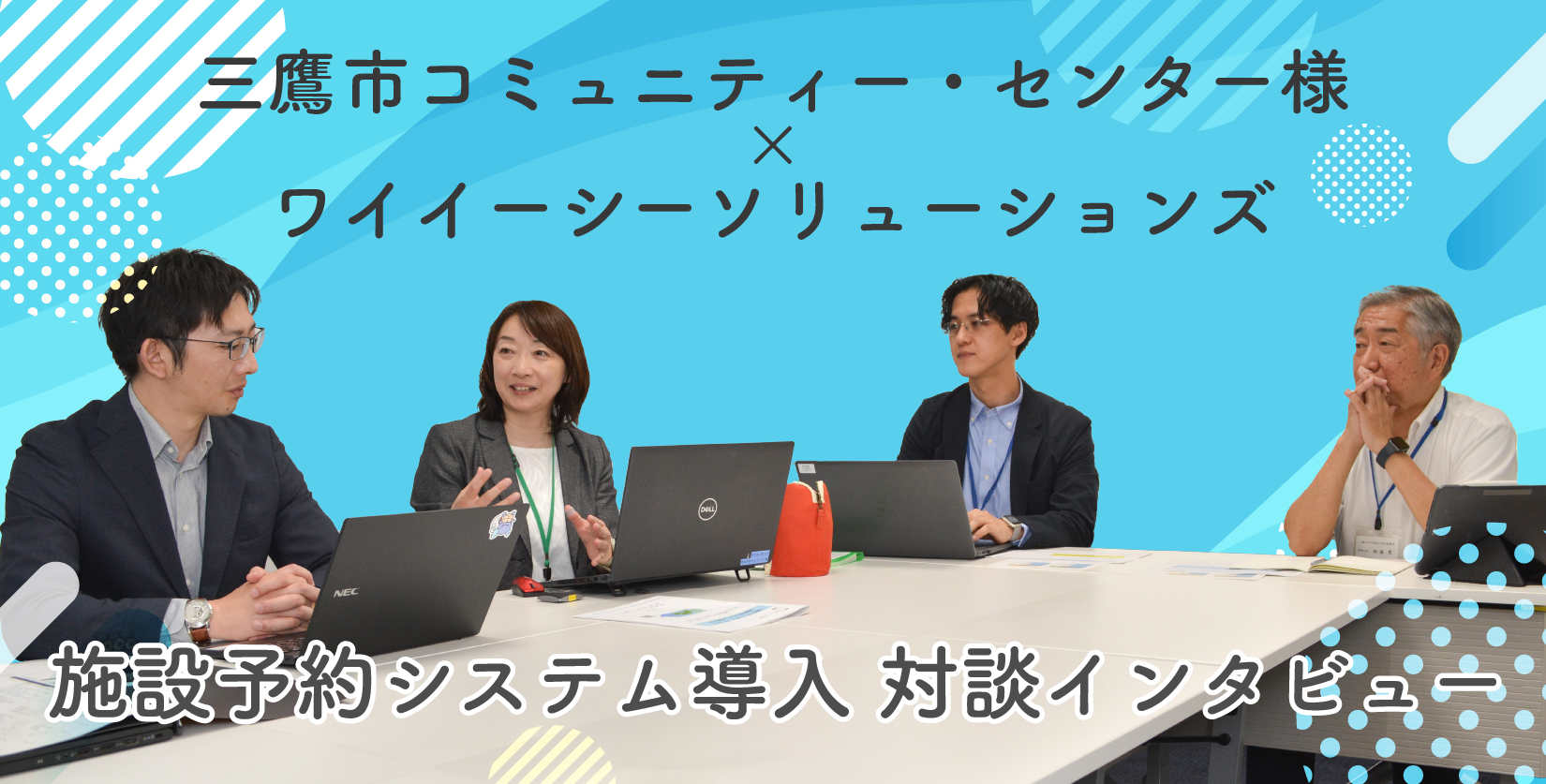通園バスに取り残された場合の危険性について
1.熱中症のリスク
特に夏場は、車内の温度が急激に上昇し、短時間でも子どもが熱中症になるリスクがあります。JAFの検証によると、エアコンを切った後の車内温度は50度近くまで上がっていました。
参考
JAF(一般社団法人日本自動車連盟) 「真夏の車内温度は短時間で危険水準に! 送迎用バスとミニバンで熱中症の危険性を検証」 2024年7月12日 https://jaf.or.jp/common/news/2024/20240712-001
2. 脱水や窒息の危険性
幼児は、自力でドアを開けたり助けを呼んだりすることが難しいため、長時間取り残されると呼吸困難や重度の脱水症状を起こす可能性があります。
3. 心理的な影響
車内に閉じ込められた子どもは、強い不安や恐怖を感じることで、精神的なショックを受ける可能性があります。このような経験により、長期的なトラウマを引き起こす可能性もあります。
通園バスに取り残さないための対策
1. バス車内の確認作業
職員は、バスが園に到着するたびに全ての座席を確認し、子どもが取り残されていないかチェックすることが重要です。確認作業を2人で行うことで、より安全になります。
2. チェックリストの活用
バス出発前および到着後に、チェックリストを用いて子どもの乗降を管理することが効果的です。チェックリストには、乗車予定の子どもの名前と人数を記載し、確認済みのチェックを付けることで、漏れを防ぐことができます。
3. 安全教育の実施
1と2の対策は、すでに多くの園で実施しているかと思いますが、職員だけでなく、保護者や子どもにも安全対策に関する教育を行うことで、より事故を防ぐことができます。
例えば、「バスを降りるときに必ず手を挙げる」「乗車と降車時には自分の名前をはっきり言う」「万が一、車内に取り残されてしまったときはクラクションを押す」などのルールを徹底することで、子ども自身も安全に対する意識を持つことができます。
4. マニュアルの作成
バスの安全確認に加え、万が一子どもが取り残された場合に備えて、迅速に対応できる体制を整えておくことが重要です。職員間での連絡方法や緊急時の手順を全職員で明確にし、定期的に訓練を行うことで、実際に事故が起きた時に迅速に対応することができます。
5. システムの活用
2023年4月より送迎バス等への安全装置の設置が義務化されました。システムを活用することで、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
しかし、これらの装置の多くは確認者がボタンを操作しなかった場合、バスのエンジンが切られてから一定時間経過するとブザーなどの警報音で知らせるため、職員が確認するまでに空白の時間が出来てしまいます。
「りりーふなっぷ びーこんうぉっち(以下、びーこんうぉっち)」は、乗車人数と降車人数を自動でカウントし、スマホアプリに人数を表示します。そのため、その場ですぐに降り忘れ・乗り忘れの園児を確認することができ、タイムラグを無くすことができます。
また、車内に設置するカメラ型のシステムに比べて工事が不要なため、初期コストを抑えて導入していただけます。さらに、スマートフォンを使って見守りを行うため、バスの台数によって初期費用が変わることはありません。
目視での確認に加え、びーこんうぉっちをダブルチェック時にご活用いただくことで、より安全対策を強化することができます。
6.まとめ
以上の対策を講じることで、通園バスに取り残されるリスクを大幅に減らすことができます。多くの園ではすでにバスの置き去り対策を行っておりますが、時折報道される幼稚園での事故により、不安に感じる保護者も少なくありません。
園児が安心して通うことができる環境を提供するためには、職員一人ひとりが高い意識をもって行動することが不可欠です。
さらに、システムで安全対策を強化することによって、安全対策に積極的に取り組んでいることのアピールにも繋がります。
\びーこんうぉっちの特長をご紹介しています/
Written with chat GPT