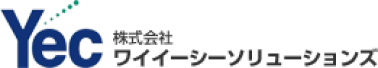属人化の実態とその背景
属人化とは、特定の個人にしか分からない業務知識やスキルが集中している状態を指します。中小企業のシステム部門では、少人数での運用が一般的であり、自然と属人化が進みやすい環境にあります。例えば、長年使用している基幹システムの保守や、過去から蓄積された業務ノウハウ、取引先とのやり取りなど、様々な場面で属人化が発生します。これは決して意図的なものではなく、日々の業務に追われる中で、自然と形成されていく状況といえます。
属人化の「良し悪し」について
一見、マイナスイメージの強い属人化ですが、実はいくつかのメリットも存在します。まず、担当者が全体を把握しているため意思決定の迅速化が図れ、関係者との調整コストを抑えることができます。また、特定分野への深い知見が蓄積され、継続的な改善や最適化が可能となります。さらに、少人数での効率的な運用が可能となり、教育・引継ぎコストの削減にもつながります。
しかし、属人化には深刻なリスクも伴います。
最も懸念されるのは事業継続性のリスクです。キーパーソンの突然の離職や病気による業務停止、知識・スキルの承継が困難になる可能性があります。また、特定個人への業務集中による負荷や、新規施策への取り組み時間の確保が困難になるという業務効率の限界も存在します。さらに、既存の方法に固執しやすく、新しい視点や改善案が生まれにくいというイノベーションの停滞も課題となります。

DX推進との両立
近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性が叫ばれる中、属人化の解消は避けて通れない課題となっています。しかし、中小企業にとって、大規模なシステム投資や人員増強は現実的ではありません。
そこで、効果的なアプローチとして、まずは重要度の高い業務から優先的に文書化を進め、簡易なマニュアルやチェックリストを作成することが挙げられます。また、低コストで導入可能なSaaSを活用し、運用負荷の軽減と標準化を促進することも有効です。さらに、フローチャートやBPMN(Business Process Model and Notation)を活用した業務の見える化を行い、属人的な判断ポイントを明確化することで、段階的な改善が可能となります。
フローチャートやBPMNを活用した業務の見える化について:具体的な解説

フローチャートやBPMNを活用した業務の見える化について、具体例を交えて説明しましょう。
例えば、「システムトラブル対応」という業務を考えてみましょう。
ベテラン担当者の頭の中では、トラブルの重要度判断、対応の優先順位付け、過去の類似事例との照合、適切な対応方法の選択、関係者への連絡判断といった一連の判断や対応が瞬時に行われています。これらの「暗黙知」は、長年の経験から培われた知識であり、まさに属人化の典型といえます。
これをフローチャートで表現することで、業務の流れと判断ポイントを可視化することができます。具体的には、トラブル発生から始まり、重要度判定、過去事例との照合、対応方法の決定、エスカレーション要否の判断、そして対応実施に至るまでの一連の流れを図示します。この過程で特に重要なのは、「属人的判断」が必要となるポイントを明確にすることです。
例えば、重要度判定の場面では、業務影響度の確認やユーザー数の確認といった判断基準が必要となります。過去事例との照合では、類似事例の有無確認や過去の解決方法の確認が行われます。また、エスカレーションの判断では、上位者への報告や取引先への連絡の要否を決定する必要があります。
このように図示することで、どの段階で属人的な判断が必要か、どのような基準で判断しているか、誰に連絡すべきかといった点が明確になります。さらに、各判断ポイントについて具体的な基準を設定することで、他の担当者でも同様の判断ができるようになります。
このように、ベテラン担当者の経験則を「見える化」し、共有可能な形にすることで、ベテラン担当者でなくても、一定の基準に従って適切な判断を下すことが可能となり、属人化の解消につながります。
コスト面での考慮点
属人化解消への取り組みには、必ずコストが発生します。
ドキュメント作成の工数、システム導入費用、教育・研修費用などの短期的なコストは避けられません。しかし、これらを「投資」として捉えることが重要です。中長期的には、リスク対策コストの削減、業務効率化による生産性向上、新規施策への取り組み余力の創出といったメリットが期待できます。

仕事のやりがいと属人化の微妙な関係性
ここで、見過ごすことのできない重要な視点があります。「属人化を解消し、誰でも実施できる業務に標準化することで、かえって仕事の面白みが失われるのではないか」という懸念です。
確かに、「自分にしかできない仕事がある」という状況は、時として大きなやりがいや誇りの源となります。長年の経験で培った独自のノウハウや、取引先との信頼関係、システムの隅々まで把握している安心感。これらは担当者の存在価値を証明し、強い職業的アイデンティティを形成する重要な要素となっているのです。
DX化による業務の標準化は、ともすれば「誰でもできる仕事」を増やすことになります。マニュアル化され、システム化された業務では、個人の専門性や経験が活きる場面が減少するかもしれません。「自分でなければ」という特別感が薄れ、仕事への愛着や責任感が損なわれる可能性も否定できません。
しかし、ここで考えたいのは、真の「やりがい」とは何かということです。確かに属人的な業務には特別な充実感があります。しかし、その一方で、属人化による負担は、新しいことに挑戦する余力を奪い、より創造的な業務に取り組む機会を制限しているかもしれません。
DX化や標準化を進めることで、これまで属人的な定型業務に費やしていた時間を、より戦略的な取り組みにシフトすることが可能となります。例えば、新しいシステムの企画立案、データ分析による業務改善の提案、あるいは部門を超えた横断的なプロジェクトのリーダーシップなど、より高度な価値創造に注力できるようになるのです。
まとめ
属人化は、中小企業のシステム部門において避けられない現実です。しかし、それを完全に否定するのではなく、メリット・デメリットを理解した上で、段階的に改善を進めていくことが重要です。DX推進との両立は確かに困難ですが、クラウドサービスの活用や業務の可視化など、実現可能な施策から着手することで、着実な進展が期待できます。
DX推進には、技術面だけでなく、経営的な視点も求められます。属人化の解消とDX推進のバランスを取りながら、組織全体の成長に貢献していくことは容易ではありません。しかし、日々の課題に向き合いながら、一歩ずつ前進を続けることが、結果として組織の発展につながっていくのです。
こちらもどうぞ
中小企業のDX化とコストの関係について、他のコラムで詳しく解説しています。